Table of Contents
「あれ?うちの愛犬、なんだか歩き方が変…?」そう感じたことはありませんか? 犬は言葉で不調を訴えることができません。だからこそ、飼い主さんが愛犬の些細な変化に気づいてあげることが大切です。今回の記事では、「犬の歩き方がおかしい場合の注意点」について、飼い主さんが知っておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。もしかしたら、それは病気や怪我のサインかもしれません。この記事を読むことで、歩き方の異常から考えられる原因、自宅でできるチェック、そして獣医さんに相談するタイミングなどが明確になります。大切な家族である愛犬の健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。
犬の歩き方がおかしい?考えられる原因とチェックポイント

犬の歩き方がおかしい?考えられる原因とチェックポイント
もしかしてどこか痛いの?考えられる原因
愛犬の歩き方がおかしいとき、まず考えられるのは痛みです。例えば、散歩中に足をぶつけたり、高いところから飛び降りたりして、骨や関節、筋肉などを痛めてしまったのかもしれません。また、加齢による関節炎もよく見られる原因の一つです。若い犬でも、成長期に骨や関節がうまく成長しない病気や、遺伝的な疾患が原因で歩き方がおかしくなることもあります。
神経系の病気も歩行異常を引き起こす可能性があります。脳や脊髄の異常、神経の損傷などが原因で、足に力が入らなかったり、ふらついたりすることがあります。その他、爪が伸びすぎて歩きにくい、肉球に異物が刺さっているといった、意外な原因も考えられます。
どんな風に歩き方がおかしい?チェックしてみよう
歩き方がおかしいといっても、その症状は様々です。例えば、片方の足をかばうようにケンケンする、後ろ足を引きずる、歩くときに腰が左右に揺れる、すぐに座り込む、階段の上り下りを嫌がる、などが挙げられます。これらの症状は、どこに異常があるのかを特定する手がかりになります。
注意深く観察することで、異常に気づけることがあります。散歩中の様子だけでなく、家の中で歩いている時や立ち上がる時など、様々な場面で愛犬の動きを観察してみましょう。動画を撮影しておくと、獣医さんに相談する際に役立ちます。
歩き方の異常 | 考えられる原因の例 |
|---|---|
ケンケンする | 骨折、捻挫、肉球の怪我 |
後ろ足を引きずる | 股関節形成不全、椎間板ヘルニア |
腰が揺れる | 股関節形成不全、変形性脊椎症 |
すぐに座り込む | 筋力低下、関節炎 |
もっと詳しく!歩行異常の種類と特徴
歩行異常には、具体的にどのような種類があるのでしょうか?例えば、「跛行(はこう)」は、足をかばうように歩く状態全般を指します。前足の跛行であれば、肩や肘、手首などに原因があるかもしれませんし、後ろ足の跛行であれば、股関節や膝、足首などに原因があるかもしれません。「ふらつき」は、平衡感覚に問題がある場合に見られます。小脳の病気や内耳の異常などが考えられます。
「起立困難」は、立ち上がるのが困難な状態です。これは、筋力低下や関節の痛み、神経系の病気などが原因で起こります。「旋回運動」は、同じ場所をぐるぐると回る行動で、脳の病気が疑われます。これらの具体的な症状を把握することで、獣医さんに的確に伝えることができます。
犬の歩き方がおかしい時に飼い主が確認すべきこと

犬の歩き方がおかしい時に飼い主が確認すべきこと
いつから?どんな時に?具体的な状況を把握しよう
愛犬の歩き方がおかしいと感じたら、まずは「いつから、どんな時にその症状が見られるのか」を具体的に把握することが大切です。例えば、「昨日の散歩の後から、右後ろ足をかばうように歩いている」とか、「朝起きた時から、立ち上がるのに時間がかかるようになった」など、できるだけ詳しくメモしておきましょう。特定の状況下でのみ症状が現れるのか(例えば、運動後、興奮時など)、時間帯によって変化があるのか(朝に症状が強い、夕方になると楽になるなど)も重要な情報です。些細なことでも構いませんので、気づいたことは全て記録しておくと、獣医さんに相談する際に役立ちます。
歩き方の異常以外に、元気や食欲の変化、排泄の状態なども確認しておきましょう。例えば、普段は喜んで散歩に行くのに、最近は嫌がるようになったり、食欲が落ちていたりする場合は、歩行異常と関連があるかもしれません。また、吐いたり下痢をしたりしている場合は、感染症や内臓の病気が原因で歩き方がおかしくなっている可能性も考えられます。これらの情報は、獣医さんが原因を特定するための重要な手がかりとなります。
触ってみよう!痛がる場所はないかチェック
次に、愛犬の体に触れて、痛がる場所がないか確認してみましょう。優しく全身を触ってみて、嫌がる部分や痛がるような反応を示す部分がないかを探ります。特に、足を痛めている場合は、指の間や肉球、関節などを丁寧に触ってみてください。腫れていたり、熱を持っていたりする部分があれば、炎症が起きている可能性があります。ただし、無理に触ると犬が痛がって噛み付く可能性もあるので、注意しながら行ってください。
もし触らせてくれないほど痛がったり、明らかに骨が折れているような場合は、無理に触らずに、すぐに動物病院に連絡しましょう。自己判断でマッサージしたり、無理に動かしたりするのは禁物です。悪化させてしまう可能性があります。獣医さんの指示を仰ぎ、適切な処置を受けるようにしてください。
確認項目 | 確認する内容の例 |
|---|---|
症状が出始めた時期 | 〇月〇日の散歩後から、〇〇してからなど |
症状が出る具体的な状況 | 散歩中、階段の上り下り、立ち上がる時など |
歩き方の異常の種類 | ケンケンする、引きずる、ふらつくなど |
その他の症状 | 元気がない、食欲不振、嘔吐、下痢など |
痛がる場所 | 触ると嫌がる、キャンと鳴くなど |
獣医さんに相談!犬の歩き方がおかしいと感じたら
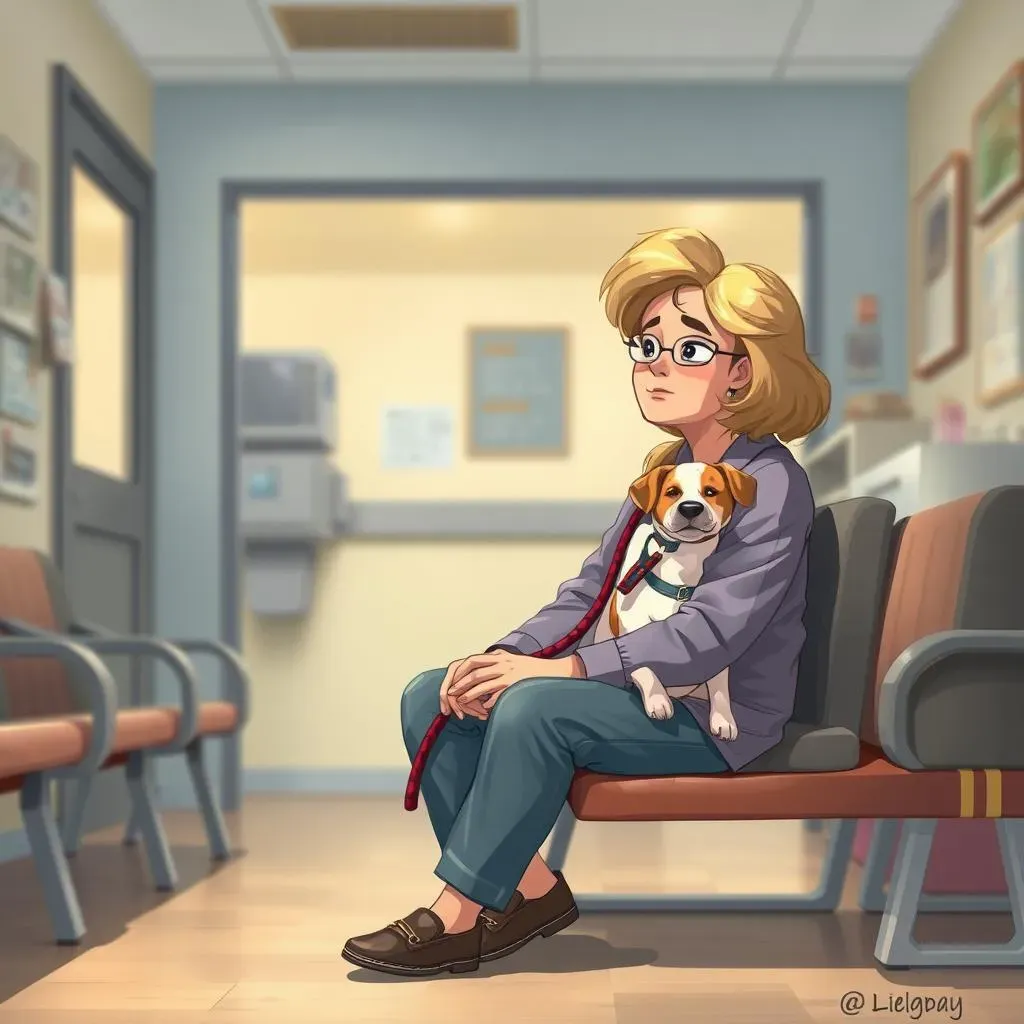
獣医さんに相談!犬の歩き方がおかしいと感じたら
ためらわずに獣医さんへ
愛犬の歩き方がおかしいと感じたら、自己判断せずに、まずは獣医さんに相談することが大切です。 「様子を見よう」と思いがちですが、早期発見・早期治療が重要な病気も少なくありません。 特に、急に歩き方がおかしくなった場合や、痛みがひどい様子が見られる場合は、迷わず動物病院を受診しましょう。 獣医さんは、専門的な知識と経験に基づいて、愛犬の状態を正確に診断し、適切な治療法を提案してくれます。 私たち飼い主ができる最善のことは、プロの力を借りることだと私は思います。
獣医さんに相談する際には、事前にメモしておいた情報が非常に役立ちます。いつから、どんな状況で症状が見られるのか、具体的な歩き方の異常、他に気になる症状はないかなどを伝えることで、獣医さんはよりスムーズに診断を進めることができます。 もし可能であれば、歩き方がおかしい時の動画を撮影しておくと、言葉だけでは伝わりにくいニュアンスも伝えることができ、診断の助けになりますよ。
どんな検査をするの?費用の目安は?
動物病院では、歩行異常の原因を特定するために、様々な検査が行われます。 一般的には、まず視診や触診で、体の状態や痛みの場所を確認します。 その後、レントゲン検査で骨の状態を調べたり、血液検査で炎症の有無や内臓の状態を確認したりすることがあります。 必要に応じて、より詳しい検査として、CT検査やMRI検査、神経学的検査などが行われる場合もあります。
気になるのは検査費用ですよね。 検査内容によって費用は大きく異なりますが、一般的なレントゲン検査であれば数千円程度、血液検査も同様の費用がかかることが多いです。 CT検査やMRI検査になると、数万円単位の費用がかかることもあります。 事前に動物病院に問い合わせて、おおよその費用を確認しておくと安心です。また、ペット保険に加入している場合は、保険が適用されるかどうかを確認しておきましょう。
検査の種類 | 目的 | 費用の目安 |
|---|---|---|
視診・触診 | 体の状態、痛みの場所の確認 | 診察料に含まれる |
レントゲン検査 | 骨折、関節の状態の確認 | 数千円程度 |
血液検査 | 炎症の有無、内臓の状態の確認 | 数千円程度 |
CT検査・MRI検査 | 詳細な画像診断 | 数万円程度 |
日頃からできること|犬の歩き方の異常を防ぐために

日頃からできること|犬の歩き方の異常を防ぐために
適度な運動と体重管理で健康な体を維持しよう
愛犬の健康な歩き方を維持するために、日頃からのケアはとっても大切です。まず、適度な運動を心がけましょう。毎日のお散歩は、筋力や関節の柔軟性を保つために不可欠です。ただし、過度な運動は関節に負担をかけてしまう可能性があるので、愛犬の年齢や体力に合わせた運動量を心がけてくださいね。例えば、若い元気な犬であれば、ボール遊びを取り入れたり、少し長めの散歩に出かけたりするのも良いでしょう。シニア犬であれば、無理のない範囲でゆっくりと散歩するだけでも十分です。
そして、体重管理も非常に重要です。肥満は関節への負担を増大させ、歩行異常のリスクを高めます。獣医さんと相談しながら、愛犬にとって適切な体重を維持できるように、食事の量や質を管理しましょう。おやつを与えすぎたり、人間の食べ物を与えたりするのは避け、バランスの取れたドッグフードを与えるようにしましょう。定期的に体重を測定し、変化に気づけるようにすることも大切です。
滑りやすい床には工夫を!生活環境を見直そう
意外と見落としがちなのが、住環境です。フローリングなど滑りやすい床は、犬の足腰に負担をかけ、関節を痛める原因になることがあります。特に、高齢の犬や関節に不安のある犬にとっては、滑りやすい床は歩行の妨げになり、転倒のリスクも高まります。カーペットやマットを敷くなどして、滑りにくい環境を整えてあげましょう。特に、犬がよく歩く場所や、立ち上がりや座り込みをする場所には、滑り止め対策を施すのがおすすめです。
また、爪のケアも忘れずに行いましょう。伸びすぎた爪は歩行の邪魔になり、関節への負担を増やす原因になります。定期的に爪切りを行うか、動物病院やトリミングサロンで切ってもらうようにしましょう。肉球のケアも大切です。乾燥しているとひび割れの原因になりますので、保湿クリームなどを塗ってケアしてあげると良いでしょう。
日頃のケア | 具体的な対策 |
|---|---|
運動 | 年齢や体力に合わせた散歩、適度な遊び |
体重管理 | 適切な食事量、バランスの取れた食事、定期的な体重測定 |
住環境 | 滑り止め対策(カーペット、マットなど)、爪切り、肉球ケア |
